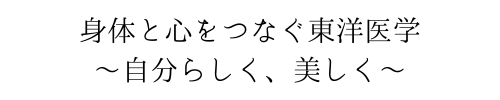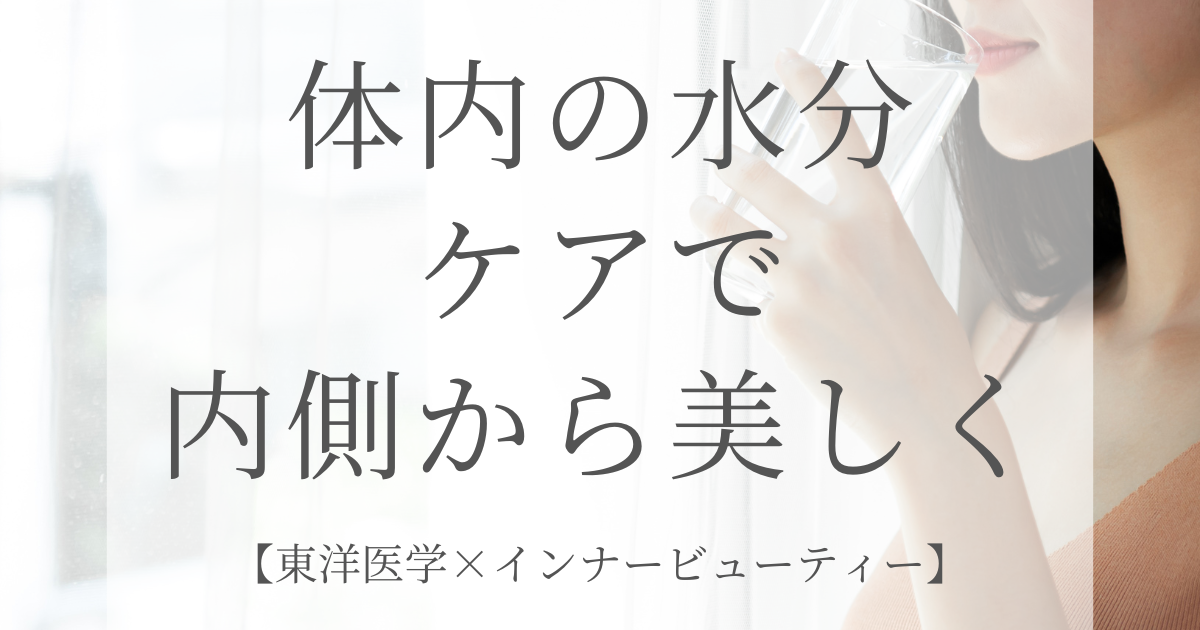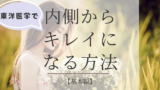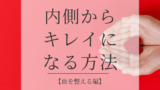こんにちは、鍼灸師のかんのです!
今回も東洋医学の観点から、身体の内側からキレイになる方法をお伝えします。

今回は「津液(しんえき)」について解説します!
津液(しんえき)って何?
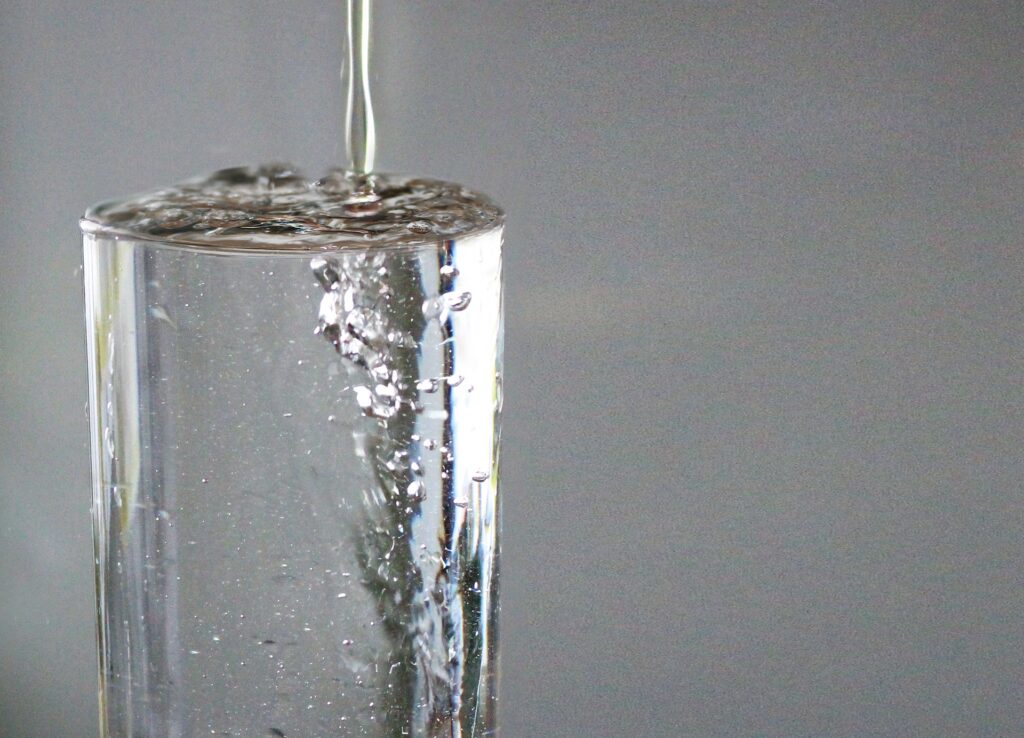
津液(しんえき)という言葉、日常生活では使わないですよね。一体どういう意味なんでしょうか?
津液(しんえき)とは、東洋医学で「体内の水分」を表します。
汗や涙、鼻水などはもちろん、細胞や内臓のうるおいを保つための水分もすべて「津液」です。

津液(しんえき)の中でも、津(しん)はさらさらとして動きやすい性質で、汗や涙、唾液などとして現れます。主に体表や筋肉を潤します。
液(えき)はねばねばとして粘性が高い性質で、関節や内臓、脳などを潤します。
津液が美容にもたらす効果

では、津液は美容にどのように関係しているのでしょうか?
肌のうるおいとツヤがアップする
津液は栄養素を含み、肌に潤いを与えてくれるため、乾燥肌・敏感肌の改善に◎。
ハリとツヤのある健康的な肌へ導きます。
むくみがとれてスッキリする
津液は全身の代謝に深く関係します。
全身に潤いを届けた後、一部は汗や呼吸で、また一部は尿や便として排出されます。
津液の循環がスムーズだと、身体の中の老廃物も一緒に排出されやすくなり、むくみの改善やデトックス効果を期待できます。
便秘が解消する
老廃物と同じように、津液の巡りが良くなるとお通じがスムーズになり、便秘が解消します。
髪がツヤツヤになる
髪がパサついたり、枝毛やうねりが出るのも、津液の代謝が悪くなっていることがひとつの原因。
津液を整えると、艶やかで丈夫な髪に近づくことができます。

東洋医学で髪は「血余(けつよ)」と呼ばれ、血と深い関係があります。
血を構成している材料は「営気(えいき)、精、津液」ですので、津液も髪の健康に深く関わっていると言えますね。
津液を整える方法
では、どうすれば津液のバランスを整えることができるのでしょうか?

日常生活に取り入れやすいポイントをいくつかご紹介します!
食事や飲み物で適切に水分を補給する
まずは水分をとることが大切!でもむやみにたくさん飲めばいいという訳ではありません。
水分をとるときは一度に大量ではなく、こまめに摂りましょう。
冷たい飲み物は体を冷やし、津液の生成に重要な脾胃のはたらきを妨げるため、常温や白湯がおすすめです。
また、食材で潤いをチャージすることも◎!
これらは体を潤す食材として、東洋医学では定番です。
お鍋に合いそうな食材は、たんぱく質と一緒にお鍋で摂取すると、水分補給と身体を温めることが同時にできて良いですね!
体内の水分を失わないようにする
サウナで整える健康法がすっかり一般的になりましたが、汗のかきすぎに注意。
汗をかいた後は水分補給をいつも以上に注意して行いましょう。
また、冷たいものや刺激物の食べ過ぎなどで下痢をすると、体内の水分が失われると同時に腸内環境も悪くなります。
脾胃で新たに津液を作り出す能力が下がってしまうので、下痢をしないように注意しましょう。
身体に熱がこもらないようにする
身体に熱がこもると、体内の津液が蒸発して消耗してしまいます。
サウナの入りすぎや、夏の暑さなど、特に温度も湿度も高い環境に注意しましょう。
ストレスは身体の中に熱を生み、津液を消耗させます。また辛いもの、脂っこいものの食べ過ぎも身体に熱を込めますのでほどほどにしましょう!
よく眠る
東洋医学的に、夜は陰の時間。津液は陰の性質があるので、夜の時間に特に補充されます。夜に充分な休息をとることがとても大切です。
寝る前に深呼吸や軽いストレッチ、ハーブティーなどでリラックス時間をとり、心地よく眠れるような環境作りから始めましょう。
軽い運動で水分代謝をよくする
津液は身体中を巡ってこそ美容と健康につながります。滞りは×!
自然界の水もサラサラと流れている時はきれいですが、一か所に滞るとよどんできますよね。
自然界で起こることは人間の体内でも起こるというのが東洋医学の考え方なので、積極的に津液の流れをよくしていきましょう!
軽いウォーキングやヨガ、ピラティス、ストレッチなどで、体の内側の水分を巡らせてあげましょう。
津液を整えて内側から美しくなろう
津液は、お肌や内臓を潤し、美容と健康を支える大切な水分。
東洋医学でインナービューティーを叶えるために欠かせないのが津液のケアです。
もちろん外側からのスキンケアも大切ですが、津液ケアを意識した食事や生活習慣で、体の内側からキレイを育ててみませんか?