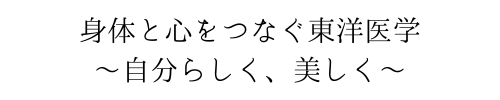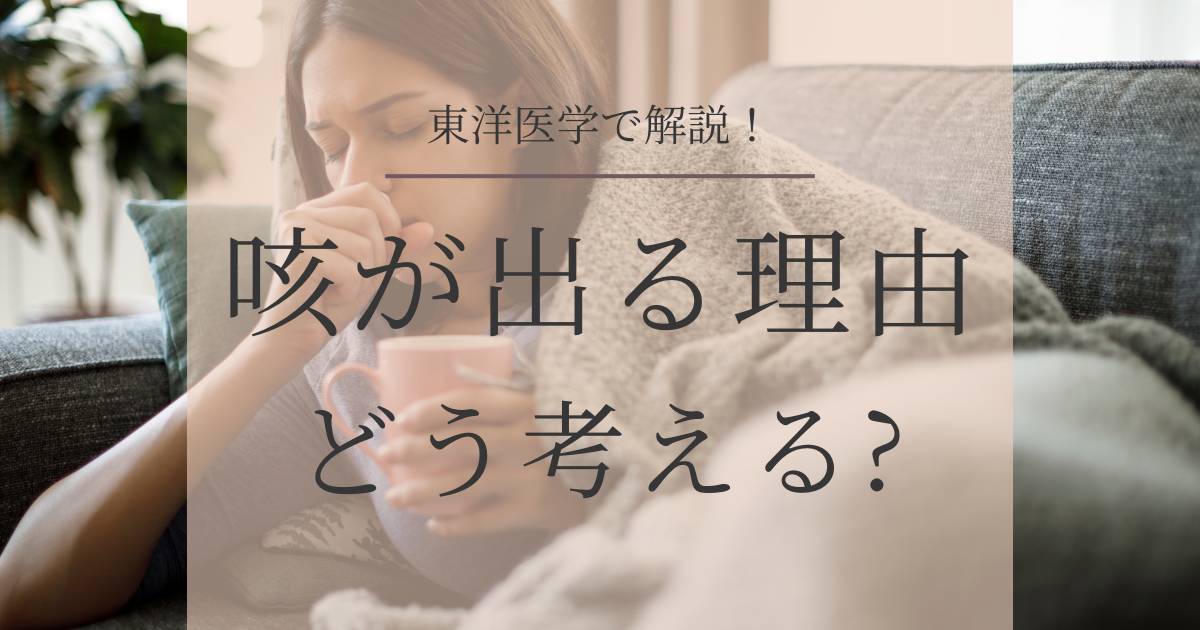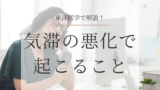こんにちは、鍼灸師のかんのです!

咳が出やすくて、風邪を引くと咳が長引きやすいです。

一度咳が出るとなかなか止まらなくて困っています。

このような咳の症状でお悩みの方、とても多いんです。
東洋医学的に、咳が出るのはどのような状態なのでしょうか?
今回は咳について、東洋医学的に考えていきましょう!
東洋医学の「咳」とは

咳といえば、どんな時に出るでしょうか?

風邪を引いた時やのどを痛めた時でしょうか。

気管支や肺の病気になった時にも咳が出そうですね。
どんな時に咳が出そうですか?という質問に対して、想像しやすいのは呼吸器系の疾患ではないでしょうか。
東洋医学でも、「肺」は呼吸において重要な役割を果たします。
本来ならば肺に留まるべき「気」が何らかの原因によって上に昇ってしまい、口から出るのが咳であると東洋医学的では考えます。
咳が出る理由
肺の気が咳として口から出てしまう原因は様々です。
これらは全部、東洋医学で咳の原因と考えられます。

呼吸器とは関係なさそうですけど・・・

その気持ち、よーくわかります。
でも東洋医学的に考えると、しっかりと説明がつくんですよ!
これが東洋医学の面白いところですね。
咳の原因を考えてみよう!

どうして咳が出るのか、教えて下さい!

それでは、咳の原因を東洋医学的に一つひとつ見てみましょう!
外から風邪などの刺激物が入ってくる
咳の理由で一番身近で想像しやすいのが「風邪」ですね。
風邪(かぜ)は、東洋医学では風邪(ふうじゃ)といいます。

他にも「寒邪(かんじゃ)」「燥邪(そうじゃ)」「熱邪(ねつじゃ)」などの「邪」シリーズがあります。
これらの刺激物が身体の中に入ってきて、肺を刺激すると咳が出ます。
刺激の強い物を食べ過ぎる
辛いものや熱いもの、冷たいものを一気に口にした時、咳が出た経験はありませんか?

私はシェイクを飲むと必ず咳が止まらなくなります・・・
辛いものや熱いもの、冷たいものなどの刺激物を食べると、
「脾」や「胃」という東洋医学の消化器官がダメージを受け、
そのダメージが肺にも影響を及ぼし咳が出ます。
イライラが込み上げてくる

イライラが咳に関係するんですか?

東洋医学では咳とイライラは重要な関わりを持っているんです。
東洋医学でイライラ等の感情の変化を司るのは「肝」という臓腑です。
イライラが溜まって肝が失調すると、熱が生まれます。その熱が肺に影響を及ぼし咳が出ます。
身体が疲れすぎている
身体の疲れは、東洋医学では「腎」という臓腑と関わっています。
「腎」は、深い呼吸に関係があるので、疲れすぎていて腎が失調していると呼吸がうまくできず、息切れがしたり咳が出たりします。
咳の理由は様々!
いかがでしたか?
東洋医学的な目線で見てみると、咳の原因は様々。
上に挙げた以外にも色々な原因が関わりあって、咳という症状になって出てきているのかもしれません。
東洋医学は、人を診る学問です。
中々治らない咳の症状でお困りの方は、東洋医学的な観点でその症状と向き合ってみるのはいかがでしょうか?
東洋医学的な治療を得意としている鍼灸院、漢方薬局で相談してみることをおすすめします!
この記事が少しでも皆さんのお役に立ちましたら幸いです♪