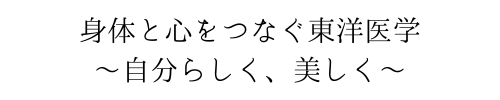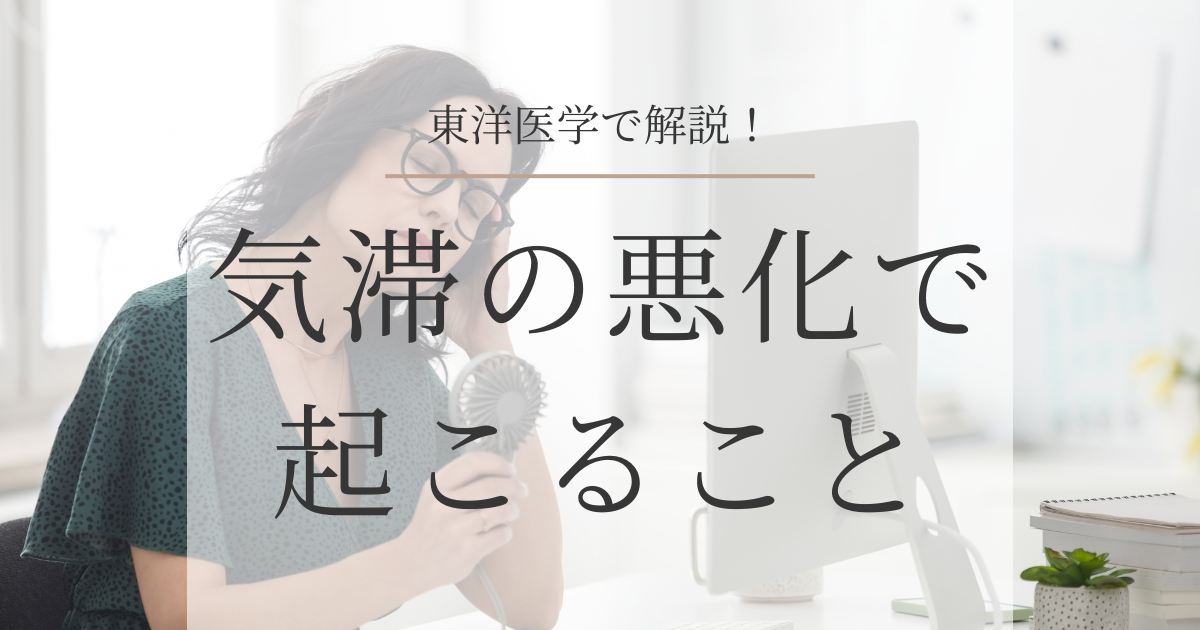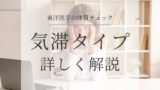皆さんこんにちは、鍼灸師のかんのです!
先日は「気滞」について詳しく解説しました。

実は、気滞を放っておくと困ったことになるんです・・・
今回は、気滞が悪化するとどんな症状が出るのか詳しく解説したいと思います!
気滞ってどんな症状?おさらいしよう
まずは肝心の「気滞」について。
気滞とは一言でいうと「体内にバランスよく循環すべき気が滞っている」状態のこと。

気滞=「気の循環障害」とも言えますね。
気滞が起こると胸やみぞおちの辺りが張って苦しくなったり、
「梅核気(ばいかくき)」と呼ばれるのどの違和感や、肩こりや頭痛などが引き起こされます。
また、イライラしやすくなったり、抑うつ感などの精神的な症状も気滞の特徴です。

常にストレスにさらされている現代人は、気滞になりやすいと言えます。
気滞を放っておくとどうなる?
ストレス発散や軽い運動などができれば気滞に上手に対処できるのですが、
忙しくて中々生活習慣を変えられない方も多いですよね。

辛いですが、何とかごまかしながら日々の生活を送っています。
という方も多いのではないでしょうか。

気持ちは分かりますが、できるだけ軽症のうちに対処しましょう!

そのまま過ごしていると気滞が次のステップへ進んでしまい、もっと面倒な状態になってしまうかもしれません。

気滞を放っておくとどうなるんですか?

気滞を放置していると、体内に熱を生み出してしまうんです!

気滞で熱・・・?どうしてですか?
気は元々エネルギーの源です。
そんな気は全身にバランスよく散布されているからこそ、体温をうまく調節したり、身体を程よく温めたりすることができます。
それがある一定の部分に固まってしまうと、そこだけに気が集まって、不必要な熱を生んでしまうのです。

この「気滞が熱を生じた状態」を東洋医学で「気鬱化火(きうつかか)」と言います。
気鬱化火(きうつかか)ってどんな症状?

何だか難しい四字熟語が出てきました・・・
「気鬱化火」になると、何が起こるのでしょうか?

詳しく解説します!
顔面がほてる
怒っている人の顔を思い浮かべてみて下さい。顔が紅くなっていると思いませんか?
これは「気鬱化火」の症状と言えます。
目が充血する、耳鳴り、頭痛
気鬱化火によって体内に熱が生じると、その熱が身体の上の方に昇っていきます。

エアコンで暖房をつけると、温かい空気はは天井近くに留まってしまいますよね。
身体の中でも同じことが起こるんです。
身体の中で発生した熱は、上に昇っていきます。
すると、目や頭、耳などに症状が出るようになります。
上に昇った熱が悪さをした結果、目の充血、耳鳴り、頭痛などが起こります。
口、のどが渇く
熱が上に昇ることによってのどの渇きを感じるようになります。
また、冷たい飲み物を好むようになることも。
身体に熱が生じることで、体内で必要な水分が蒸発してしまうので、のどが渇くのですね。
最近冷たい飲み物を好むようになった方は、身体で発生した熱をどうにかして下げたい!という身体からのサインかもしれません。
便秘になる
身体に熱がこもって水分が蒸発すると、お通じに行くはずだった水分も消耗してしまうので、便秘傾向になります。
急に便秘気味になった方は、身体に熱がこもっている可能性があります。
月経の問題が起こる
身体に熱がこもった状態になると、月経の周期が早まる傾向にあります。
また月経血の量が増加したり、PMSが悪化して気持ちの浮き沈みが激しくなることも。
精神的に不安定になる
不安感や焦燥感で胸がザワつく、集中力が低下する、睡眠障害などの症状も現れることがあります。
咳が出る
肝の失調で熱が生み出されると、その熱が上に昇っていき、肝よりも上にある「肺」を刺激します。
その刺激により、咳が止まらなくなることがあります。
イライラで咳が止まらなくなることがある方は、これが原因かもしれません。
気滞の解消に重要な臓腑は「肝」!

「気滞」から「気鬱化火」への変化についてはわかりました。
どうやって対処したらいいですか?

詳しく解説します!
ここで東洋医学的に忘れてはいけない「臓腑」の話をしたいと思います!
東洋医学的に、ストレスと深く関わる臓腑は「肝」です。

東洋医学の「肝」と、西洋医学の「肝臓」では、名前が似ていますが働きは大きく異なります。
東洋医学の「肝」は、体内の気の流れを調節したり、感情のバランスを整える作用があります。
そんな肝の作用が失調すると、気滞の中でも特に肝に関係のある「肝鬱気滞(かんうつきたい)」という病証になります。
肝鬱気滞が進行すると、気鬱化火になります。
気滞を悪化させないためには肝をいたわる必要があります!
肝をいたわる生活を心がけよう
では、肝をいたわる為にはどうしたらよいのでしょうか?
ストレスを溜めない
肝をいたわるためには、何よりもストレスを溜めないことが大切!
前回の記事でもご紹介していますのでぜひ見てみて下さい♪
食べ物に酸味を取り入れる
まず食べ物に酸味を取り入れてみましょう!
適度な酸味は肝の働きを高め、気滞の解消に役立ちます。
酸味は消化を助ける作用もあり、胃の働きを良くしてくれるので、身体全体の気の循環の改善にも役立ちます。
最近コンビニに行くと、酸っぱい味のグミが豊富に取り揃えられているのを目にしませんか?
これはストレス社会で戦う皆さんが無意識のうちに酸味を欲しているからではないか・・・と思っています。
グミも美味く手軽に酸味を取ることができますが、砂糖がたくさん使われている場合もありますので注意!
過剰な甘味は消化吸収に携わる「脾」と「胃」の働きを悪くしてしまいます。
ぜひ、梅干しや柑橘類などの自然な酸味を日常に取り入れてみて下さい!
熱を生む食材を避ける
辛いものや脂っこいものは身体の中で熱を生みやすいので、食べ過ぎ注意です。
お酒も程々にしておきましょう!
お酒は西洋医学的にも肝臓に良くないですが、東洋医学的にも過剰な飲酒は情緒を不安定にし、気の流れを悪くする要因になります。
お酒を飲むと身体が熱くなりますよね。お酒も身体に熱を溜めこみやすいので注意です。
養生が肝心!
いかがでしたか?
気滞が進行すると面倒であるということがお分かり頂けたのではないでしょうか。
何事も、進行してしまうと元の状態に戻すのは大変です。
症状が比較的軽いうちに、養生して解消できるものは解消していきましょう!
それでも中々ご自身だけで健康管理するのは大変ですよね。
そんな時は私たちのような東洋医学を専門にする鍼灸師に頼って下さいね。
どうぞお身体大切に、養生なさってください♪